トウキョウXは、高価格・固定価格で取引されるため、肉豚1頭あたりの売上・利益が高い水準で安定しています。
新規投資や固定費を抑えつつ、一頭一頭をていねいに育て、高品質で高付加価値の豚肉を提供するビジネスモデルには、未来への大きな可能性があります。
持続可能な養豚経営の一環として、トウキョウXの導入を検討してみませんか。
都外生産
可能!
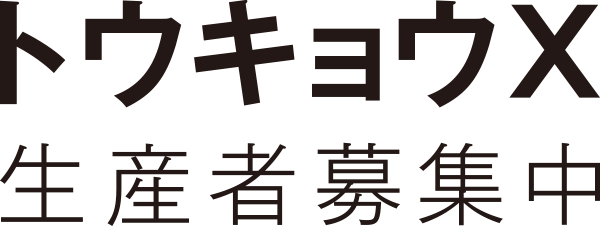
トウキョウXは、高価格・固定価格で取引されるため、肉豚1頭あたりの売上・利益が高い水準で安定しています。
新規投資や固定費を抑えつつ、一頭一頭をていねいに育て、高品質で高付加価値の豚肉を提供するビジネスモデルには、未来への大きな可能性があります。
持続可能な養豚経営の一環として、トウキョウXの導入を検討してみませんか。